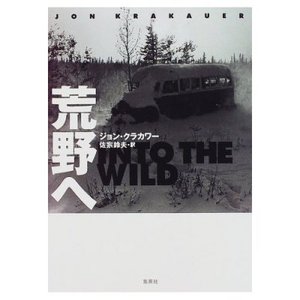先日、映画を観た"into the Wild"の原作『荒野へ』(ジョン・クラカワー著 集英社文庫)を読んでいる。
美しくて、悲しい映像の記憶を呼び覚まされながら、映画では伝えきれなかった細部の物語に、引き込まれている。
23歳の主人公クリスと出会った80歳のロンは、映画では出会いと別れの場面しか登場していないが、後にクリスから 「この世は驚きに満ちています......外へ出て、自然の造形と接し、人と出会わなくてはいけません」と手紙を受け取り、 その孫のような青年のアドバイスを真剣に受け取って、自らも荒野の住人となる。
かつて、クリスが寝起きしていた砂漠の片隅に小さなサイトを築き、そこで再会を約束したクリスを待ち続ける。
クリスとの交流の中で、ロンはクリスが家族との軋轢を抱えていることに気づいて、「いつか、許せる時が来る。そしたら、 神の祝福がもらえるよ。光が見えるんだ」と若者を励ます。
クリスが荒野に散ったと知ったとき、ロンは信仰を捨てる。
『私は祈ったんだ。アレックスの肩にかけた指を話さないでください、と神に願いごとをしたわけさ。あれはとくべつな若者だって、 神に言ったんだよ。だけど、神はアレックスを死なせてしまった。それで、なにが起こったか、私は12月26日に知り、神を捨てた......』
映画では、クリス(アレックスと名乗っていた)が亡くなる瞬間、雲間から光が射し込み、それが彼の顔を浮かび上がらせる。それまで、 苦悶していた彼の表情は、うっすらと笑みを浮かべる。
荒野へ向かった若者は、結局、自分の内側へその深奥へと旅を続けていたのだろう。そして、彼と関わった全ての人たちもまた、 彼の影響で、自分の深奥へと向かっていくことになったのだろう。
ぼくは、10代の終わり頃から、一人旅とソロの山行を始めた。
それまで、日記などまともにつけたことはなかったのだが、小さなフィールドノートを用意して、 そこに自分の気持ちを書き付けるようになった。若い頃のその日記は、今でも宝物としてとってある。
クリスが、野宿の夜に、左手に不器用な持ち方でペンを握って、アルファベットの大文字で、その時々の思いを綴っていく姿は、 そのまま、自分の若い頃のテントの中での姿だった。
彼が長じて、今のぼくくらいの歳になっていたら、いったいどんな生活を送っていただろう。
どんなに辛いことがあっても、今、ぼくは「生」を与えられている。それを感謝して、ただ流されていくのではなく、時々、into the Insideの旅へ戻らなければいけないのだと思う。