カルチャー [書評]
風景と記憶
文:内田一成
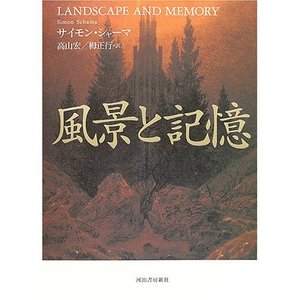
(河出書房新社 サイモン・シャーマ著 高山宏/栂正行訳)
人は風景の中に何を見るのか。そして風景には人の記憶がどう織り込まれ、人に何を語ろうとしているのか。
「無垢の自然」、「手つかずの自然」といった言葉を人は好んで使うが、じつは人跡未踏で、誰の手も加わっていないように思える土地でも、人の手によって自然が改変され、それが逆に好ましい安心感や居心地の良さを生み出して錯覚させていることがある。
たとえば、アメリカで最初に国立公園に指定されたヨセミテは、自然保護の父ヘンリー・デイビッド・ソローやジョン・ミューアが賞賛し、アンセル・アダムスが生涯に渡って風景を記録した場所だが、その「荒野」はアワネーチーインディアンが何十世代にもわたって野焼きを行って、自然を管理してきた場所だった。
日本でも、我々が心を刺激される自然風景の多くは、原始そのままのものよりは、どこかに人の手が入っているもののほうが多い。
そういった「自然の風景」という言葉に染みついた第一印象を著者サイモン・シャーマは、まず解体する。そして、歴史学者として古代から、ギリシア・ローマ、中世、近代、現代という時間軸をベースとしながら、世界中のあらゆる場所へと思考を広げ、人と風景の関わり合いと歴史的事象に風景が与えた影響を紐解いていく。
風景と歴史の関わり合いといったことを、ここまで掘り下げた研究はいまだかつてなかったものだ。シャーマが語る風景に織り込まれた人の歴史や、建築や絵画、文学の中に潜むメタファとしての風景を明らかにしていくと、そこには心理分析やポリティカルな分析では拾い上げられない人の営みや精神が暴き出されていく。
ユダヤ人であるシャーマは自分の親たちが遭遇したポグロム(大量虐殺)の記憶を辿りながら、東欧の静かな里山に分け入る。そこには池を見下ろす明るい草地に白い自然石が整然と並べられ長閑に風に吹かれている。その風景に秘められた歴史を知らなければ、そこはまさに「楽園」と呼んでも良さそうな快適な土地に見える。その彼の私的体験から、さらにナチスドイツの遺産として残された自然豊かな風景が、「全風景改変計画」の名のもとに、住民たちを虐殺して、ゲルマン的に好ましい「自然」に作り替えられて今に残ることなどが語られる。
たとえば、伸びやかで明るい北海道のあの光景も、その裏には先住民であるアイヌの虐殺や、大陸や朝鮮半島から強制徴用された人たちの命と引き替えに作り上げられたものであることも思い出す必要があるだろう。
もう20年以上も前、初めて北海道をオートバイでツーリングしたときに、荒野を真っ直ぐに切り開いて伸ばされた広いダートロード(網走と内陸を結ぶ幹線国道だが当時はほとんど舗装されてはいなかった)を走りながら、道の両側に丸い塚のような土盛が並んでいる光景を不思議に思った。後で土地の人に尋ねると、「あれは強制労働させられた囚人の墓だよ」と、あっさり答えられ、一ライダーとして素朴に信奉していた「北の大地」のイメージが、いかに皮相なものであったかを思い知らされた。
もちろん、シャーマは『風景と記憶』の中でそういった悲劇の歴史を語っているだけではない。ここには、風景にインスパイアされて、神話を生みだし、またその神話を建築や芸術に再表現して、自然を賞賛する人間の営みも豊富に紹介されている。
相当な大著だが、いわゆるポストモダンの文脈に立った難解な言説はなく、淡々と事実を積み重ねて物語られていくので、この種の著作としては平易に読み進められる。
最新記事
- The Mysteries of Harris Burdick (2011年11月28日)
- Physics of the Future (2011年7月 8日)
- 瀬戸内国際芸術祭でトークライブ(2010年10月21日)
- "Born to Run 走るために生まれた" (クリストファー・マクドゥーガル)(2010年5月15日)
- 『レイラインハンター --日本の地霊を探訪する--』(2010年4月16日)
この記事のトラックバックURL
https://e4.gofield.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/251
